定年を迎え、新たな一歩を踏み出そうとする60代。セカンドキャリアへの期待とともに、「転職後の年収はどれくらいになるのだろう?」「今の生活を維持できるだろうか?」といった経済的な不安は、誰しもが抱える切実な悩みではないでしょうか。
かつてのように「定年後は悠々自適」とはいかない時代、多くの方が60歳を過ぎても働くことを選択しています。しかし、若い頃と同じ感覚で転職活動に臨むと、思わぬ壁にぶつかることも少なくありません。
この記事では、60代の転職と年収というテーマに真正面から向き合います。公的なデータを基にしたリアルな年収事情から、収入を維持・向上させるための具体的な仕事選び、年金や税金といった必ず知っておくべきお金の知識、そして転職を成功に導くためのステップまで、網羅的に解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたは漠然とした不安から解放され、自信を持ってセカンドキャリアのプランを設計できるようになっているはずです。さあ、一緒に戦略的な計画を立て、充実した未来への扉を開きましょう。
60代の平均年収はいくら?雇用形態別の実態
厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、60代の平均年収(※)は以下のようになっています。
| 年齢階級 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 60~64歳 | 約341.6万円 | 約267.4万円 |
| 65~69歳 | 約302.2万円 | 約237.9万円 |
※賃金(月額)×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額で算出。
50代後半(55~59歳)の平均年収が男性で約440万円、女性で約288万円であることと比較すると、60代になると収入が大きく減少する傾向にあることがわかります。
この背景には、雇用形態の変化が大きく影響しています。同調査では、60代になると正社員(正職員)の割合が減り、パートタイマーなどの非正規雇用の割合が増加します。
- 正社員の場合: フルタイムで働くため、比較的高い年収を維持しやすい傾向にあります。
- 契約・嘱託社員の場合: 正社員よりは給与水準が下がることが多いですが、専門性を活かせれば高収入も可能です。
- パート・アルバイトの場合: 労働時間が短くなるため、年収は大きく下がります。年収100万円~200万円台が中心となります。
自身の希望する働き方や生活スタイルに合わせて、どの程度の収入が見込めるのかを具体的にイメージするための基礎知識として、これらのデータを押さえておきましょう。
転職で年収が下がりやすい理由とは
なぜ60代の転職では年収が下がりやすいのでしょうか。主な理由は以下の通りです。
- 役職定年による役割の変化: 多くの企業では、60歳前後で管理職から外れる「役職定年」制度があります。マネジメントの役割から外れ、プレイヤーとしての役割に変わることで、役職手当などがなくなり給与が下がります。
- 労働時間の短縮: 体力的な配慮やワークライフバランスを重視し、フルタイムから時短勤務や週3~4日勤務へ切り替えるケースが増えます。労働時間が減れば、当然収入も減少します。
- 非正規雇用の割合増加: 60代向けの求人は、正社員よりも契約社員やパート・アルバイトの募集が多いのが実情です。これにより、平均年収が押し下げられます。
- 給与体系の違い: これまで勤めていた企業の給与水準が高かった場合、同等の給与を提示できる転職先を見つけるのは容易ではありません。特に中小企業へ転職する場合、給与体系そのものが異なるため年収ダウンに繋がります。
これらの構造的な理由を理解しておくことで、「年収が下がるのは仕方ない」と諦めるのではなく、「どうすれば収入を維持できるか」という戦略的な思考に繋げることができます。
比較|継続雇用(再雇用)と転職のメリット・デメリット
定年後の選択肢として最も一般的なのが、同じ会社で働き続ける「継続雇用(再雇用・勤務延長)」と、新たな職場を探す「転職」です。それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。
| 項目 | 継続雇用(再雇用) | 転職 |
|---|---|---|
| メリット | ・慣れた環境、人間関係で働ける安心感 ・仕事内容を把握しており、精神的負担が少ない ・転職活動の手間がかからない |
・年収維持、向上の可能性がある ・新たなスキルや経験が得られる ・心機一転、新しい環境で働ける ・希望の働き方(勤務地、時間)を選べる |
| デメリット | ・給与が大幅に下がるケースが多い ・仕事内容や役割が変わり、モチベーション維持が難しいことがある ・元部下や後輩が上司になることがある |
・希望条件に合う求人が見つかりにくい ・新しい環境や人間関係への適応が必要 ・転職活動に時間と労力がかかる ・年収が下がるリスクもある |
どちらが良いという絶対的な正解はありません。安定や慣れた環境を重視するなら継続雇用、年収や新たな挑戦を重視するなら転職というように、ご自身の価値観やライフプランに合わせて慎重に判断することが大切です。
60代の転職を成功させる具体的ステップ

ここからは、60代の転職活動を成功に導くための具体的な4つのステップを解説します。若手の転職とは異なる、60代ならではの戦略で進めていきましょう。
STEP1:キャリアの棚卸しと市場価値の把握
転職活動の第一歩は、敵(転職市場)を知る前に、己(自分自身)を知ることから始まります。それが「キャリアの棚卸し」です。
【何を】
これまでの職務経歴を時系列で書き出すだけでは不十分です。以下の点を具体的に掘り下げて整理しましょう。
- 経験業務: どのような部署で、どんな業務を担当してきたか。
- 習得スキル: 専門知識(経理、法務、技術など)、語学力、PCスキルなど。
- 実績・成果: 「〇〇を改善し、コストを△%削減した」「部下を□人育成し、チームの売上を◇%向上させた」など、具体的な数字で示せる実績。
- 保有資格: 業務に関連する資格や、今後活かせそうな資格。
【なぜ】
この作業の目的は、自身の「強み」と「市場価値」を客観的に把握することです。自分では当たり前だと思っていた経験が、他の企業にとっては非常に価値のあるスキルかもしれません。棚卸しをすることで、応募すべき職種や業界、そしてアピールすべきポイントが明確になります。
【どうやって】
ノートやPCの文書作成ソフトに、思いつくまま書き出してみましょう。家族や信頼できる元同僚に話を聞いてもらうのも、自分では気づかなかった強みを発見する良い機会になります。
≪シナリオ例:長年、経理畑を歩んできたBさん(61歳)の会話≫
Bさん: 「私はずっと経理一筋で、特別なことなんてしてきませんでしたよ…」
キャリアアドバイザー: 「Bさん、そうおっしゃらずに。例えば、何か業務を効率化した経験はありませんか?」
Bさん: 「ああ、そういえば10年ほど前に、手作業だった経費精算をシステム化するプロジェクトを担当しましたね。導入当初は反発もありましたが、最終的には月20時間ほどかかっていた作業が5時間くらいに短縮できて、みんなに喜ばれました。」
キャリアアドバイザー: 「素晴らしい実績じゃないですか!それは『業務改善提案力』と『プロジェクト推進能力』という立派なスキルです。多くの中小企業では、そうした経験を持つ人材を求めているんですよ。」
STEP2:60代に特化した求人の探し方
やみくもに求人を探しても、時間と労力がかかるだけです。60代の採用に積極的な企業と効率的に出会うためのチャネルを活用しましょう。
- シニア向け転職エージェント・求人サイト:
「マイナビミドルシニア」「FROM40」など、ミドル・シニア層に特化したサービスが多数あります。専門のキャリアアドバイザーがキャリアの棚卸しから求人紹介、面接対策までサポートしてくれるため、初めての転職でも安心です。 - ハローワーク:
各地域のハローワークには「生涯現役支援窓口」など、高齢者の就職を専門にサポートする窓口が設置されています。地域に密着した求人が多く、相談員から直接アドバイスをもらえるのが強みです。 - シルバー人材センター:
地域社会に貢献したい、無理のない範囲で働きたいという方におすすめです。比較的軽作業や短時間の仕事が中心ですが、安定して仕事を得やすいというメリットがあります。 - リファラル採用(縁故・紹介):
これまでのキャリアで築いた人脈を活かす方法です。元同僚や取引先などに声をかけてみることで、思わぬチャンスに繋がることがあります。信頼関係がベースにあるため、ミスマッチが起こりにくいのも特徴です。
STEP3:経験を強みに変える応募書類の書き方
応募書類(履歴書・職務経歴書)は、企業との最初の接点です。ここで「会ってみたい」と思わせることができなければ、面接には進めません。
【多くの方が見落としがちなポイント】
60代の職務経歴書で最も重要なのは、冒頭の「職務要約」です。
採用担当者は多忙で、すべての職歴をじっくり読む時間はありません。若手のように時系列で職歴を長々と書くのではなく、最初の100~200文字程度で「自分は何者で、貴社にどう貢献できるのか」を簡潔にアピールしましょう。
<職務要約の悪い例>
1985年に〇〇株式会社に入社後、営業部に配属。その後、人事部、総務部を経て、2020年に経理部長に就任。2024年に定年退職しました。
→ これでは、何ができる人なのかが伝わりません。
<職務要約の良い例>
約40年間、メーカーの管理部門で経験を積んでまいりました。特に直近10年間は経理部長として、月次・年次決算業務の早期化や経費精算システムの導入による業務効率化(月間20時間の工数削減)を実現しました。この経験を活かし、貴社のバックオフィス体制の強化に即戦力として貢献できると考えております。
→ 具体的な実績と貢献意欲が明確に伝わります。
職務経歴の本文では、応募する企業の求人内容に合わせて、関連性の高い経験を重点的に記述し、それ以外は簡潔にまとめる「選択と集中」が鍵となります。
STEP4:面接対策|健康・意欲・柔軟性の伝え方
書類選考を突破したら、いよいよ面接です。企業側が60代の採用で懸念しがちなのは、主に以下の3点です。
- 健康面: 「体力的に業務を継続できるか?」
- 柔軟性: 「年下の上司や同僚と上手くやっていけるか?」「新しい環境ややり方に順応できるか?」
- 学習意欲: 「新しいことを覚える意欲があるか?」
面接では、これらの懸念を払拭し、安心感を与えることが何よりも重要です。
≪シナリオ例:面接での想定問答≫
面接官: 「失礼ですが、健康面で何か懸念されていることはございませんか?」
応募者: 「ご質問ありがとうございます。健康管理には特に気を配っており、毎朝のウォーキングを5年以上続けています。先月の健康診断の結果もすべてA判定で、医師からも太鼓判を押されています。フルタイム勤務も全く問題ございません。」
面接官: 「弊社では、30代の社員がチームリーダーを務めることもありますが、年下の上司のもとで働くことに抵抗はありますか?」
応募者: 「全くございません。年齢に関わらず、役職者が上司であると認識しております。これまでの経験で何かお役に立てることがあればサポートさせていただきたいですし、逆に新しいやり方については、謙虚に教えを請い、一日も早くキャッチアップしたいと考えております。」
このように、具体的なエピソードを交えながら、前向きで誠実な姿勢を示すことが、信頼獲得に繋がります。
よくある質問と回答(Q&A)

ここでは、60代の年収や転職に関して多くの方が抱く疑問に、Q&A形式でお答えします。
Q. 未経験の職種に挑戦できますか?
A. はい、挑戦は十分に可能です。ただし、成功には戦略が必要です。
20代の若手のようにポテンシャルで採用されることは難しいため、「なぜこの仕事に挑戦したいのか」という熱意と、「その仕事で活かせる自分の強み」を明確にアピールすることが不可欠です。
<狙い目の分野>
- 人手不足の業界: 介護、運送、警備、清掃などは常に人手を求めており、未経験のシニア人材を積極的に採用しています。
- コミュニケーション能力が活かせる仕事: 販売スタッフ、営業サポート、コールセンターなど、これまでの社会人経験で培った対人スキルが強みになります。
<成功のポイント>
- 資格取得: 挑戦したい分野の入門的な資格(例:介護職員初任者研修)を取得すると、意欲の証明になります。
- 現実的な年収目標: 未経験からのスタートは、年収が下がる可能性が高いことを覚悟しておきましょう。新たなキャリアを築くための投資期間と捉える視点も大切です。
Q. 体力的に無理なく働ける仕事はありますか?
A. はい、たくさんあります。ご自身の健康状態に合わせて選ぶことが重要です。
身体的な負担が少なく、長く続けやすい仕事として以下のようなものが挙げられます。
- 事務職: データ入力、書類作成、電話応対など。PCスキルは必須ですが、座り仕事が中心です。
- マンション管理員: 居住者の対応や簡単な清掃、点検業務が主で、自分のペースで働きやすい仕事です。
- 受付・インフォメーション: 企業の顔として来客対応を行います。丁寧な言葉遣いや対応力が求められます。
- 軽作業: ピッキングや検品、梱包など。立ち仕事が多いですが、そこまで重いものを持たない職場も多数あります。
<もし体力的にフルタイム勤務などが難しい場合は?>
求人を探す際に「週3日勤務」「1日5時間」「時短勤務可」といった条件で絞り込んでみましょう。また、専門スキルがあれば、業務委託契約で自宅から自分のペースで働ける仕事を見つけるという選択肢もあります。無理をせず、長く続けられる働き方を見つけることが最も大切です。
Q. 年収交渉は可能ですか?
A. 可能性はありますが、若手と同じ感覚では難しいのが現実です。
年収交渉が成功するかどうかは、「企業が提示額以上の価値をあなたに認めるかどうか」にかかっています。交渉の土台となるのは、客観的で明確なスキルや実績です。
<交渉の余地が生まれやすいケース>
- 専門性の高い職種: 経理、法務、技術者など、代替のきかない専門職。
- 実績が企業の利益に直結する場合: 「前職で培ったこの人脈を使えば、貴社に新たな販路を開拓できます」といった具体的な貢献を提示できる場合。
- 複数の企業から内定を得ている場合: 他社の提示額を基に交渉することも可能ですが、伝え方には細心の注意が必要です。
交渉する際は、内定が出てから、承諾の返事をする前のタイミングで行います。自身の市場価値や同業・同職種の給与水準をリサーチした上で、「〇〇というスキル・経験を活かして貢献できるため、〇〇円を希望いたします」と、謙虚かつ論理的に希望を伝えることが重要です。
Q. 転職活動にかかる期間はどれくらいですか?
A. 一般的には3ヶ月から6ヶ月程度が目安ですが、個人差が非常に大きいです。
応募する職種や希望条件、活動のペースによって期間は大きく変動します。特に、好条件の求人や専門職を狙う場合は、半年から1年近くかかることも珍しくありません。
大切なのは、焦らないことです。「なかなか決まらない」と焦って、希望しない条件の会社に妥協して入社してしまうと、早期離職に繋がりかねません。セカンドキャリアは、これからの人生を豊かにするための大切な選択です。
可能であれば、定年退職する数ヶ月前から情報収集を始めるなど、経済的・精神的に余裕を持って計画的に進めることをお勧めします。
実践のためのヒントとコツ
最後に、充実したセカンドキャリアを実現するための3つのヒントとコツをお伝えします。
ヒント1:経験を活かすか、需要に応えるか。「仕事選びの2軸」を持つ
60代の仕事選びは、大きく分けて2つの方向性があります。
- 経験活用ルート: これまで培った専門性(経理、人事、技術開発など)を活かし、中小企業の顧問やコンサルタント、専門職として働く道です。年収を維持・向上させやすいのが最大のメリットです。
- 市場需要ルート: 介護、運送、ビルメンテナンスなど、人手不足でシニアの活躍が期待される業界に飛び込む道です。未経験からでも挑戦しやすく、社会貢献の実感を得やすいのが特徴です。
どちらのルートが自分に合っているか、キャリアの棚卸しを通じて見極めましょう。
ヒント2:【盲点】年収を左右する「お金の知識」を味方につける
60代の働き方を考える上で、給与の額面だけを見るのは非常に危険です。「年金」や「公的給付金」の知識が、手取り収入を大きく左右します。
- 在職老齢年金: 60歳以降、厚生年金に加入しながら働くと、給与と年金の合計額に応じて年金が減額または支給停止される制度です。2024年4月現在、合計額が50万円を超えると調整の対象となります。「働きすぎて年金が減らされ、かえって手取りが減った」という“働き損”を避けるため、この仕組みは必ず理解しておきましょう。
- 高年齢雇用継続給付金: 60歳以降の給与が60歳時点に比べて75%未満に低下した場合、雇用保険から給付が受けられる制度です(※支給要件あり)。再雇用などで給与が下がった際の収入を補う重要な役割を果たします。
これらの制度を知っているかどうかで、年間の手取り額が数十万円単位で変わることもあります。転職活動と並行して、年金事務所やハローワークで自身の状況について相談することをお勧めします。
ヒント3:正社員にこだわらない「柔軟なキャリアプラン」を描く
年収や安定を求めて正社員を目指すのは一つの選択肢ですが、それが全てではありません。
- 契約・嘱託社員: 期間は決まっていますが、特定のプロジェクトや業務に集中できます。
- パート・アルバイト: 働く時間を調整しやすく、趣味や家族との時間を大切にできます。
- 業務委託・フリーランス: 専門スキルを活かし、時間や場所に縛られずに働くことができます。
「収入」「やりがい」「健康」「プライベート」など、自分が何を最も大切にしたいのかを考え、多様な働き方の中から最適なバランスを見つけることが、満足度の高いセカンドキャリアの鍵となります。
まとめ:戦略的な計画で、60代の転職と年収の最適解を見つける

本記事では、60代の転職における年収の現実から、収入を維持・向上させるための具体的な戦略、そして成功へのステップを詳しく解説してきました。
【本記事の重要ポイント】
- 現実を知る: 60代の平均年収は下がる傾向にあるが、雇用形態や職種で大きく異なることを理解する。
- 戦略を立てる: 経験を活かすか、人手不足の業界を狙うかなど、自身の強みと市場の需要を掛け合わせて仕事を選ぶ。
- ステップを踏む: 「キャリアの棚卸し → 求人探し → 書類作成 → 面接対策」という手順を丁寧に進める。
- お金の知識を学ぶ: 在職老齢年金などの制度を理解し、手取り収入を最大化する働き方を考える。
- 柔軟に考える: 正社員にこだわらず、自身の価値観に合った多様な働き方を視野に入れる。
60代からのキャリアは、決して「終わり」ではありません。これまで培ってきた豊富な経験と知識は、あなたにしかない貴重な財産です。変化を恐れず、戦略的に準備を進めることで、年齢はハンデではなく、むしろ強みになります。
まずは、ご自身のキャリアをじっくりと振り返ることから始めてみませんか。その一歩が、経済的な安定と生きがいに満ちた、充実のセカンドキャリアへと繋がっていくはずです。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の状況に対する法的な助言や医療行為の代替となるものではありません。年金、税金、各種公的制度の利用にあたっては、必ず日本年金機構、ハローワーク、税務署、または社会保険労務士、税理士といった専門家にご確認・ご相談ください。
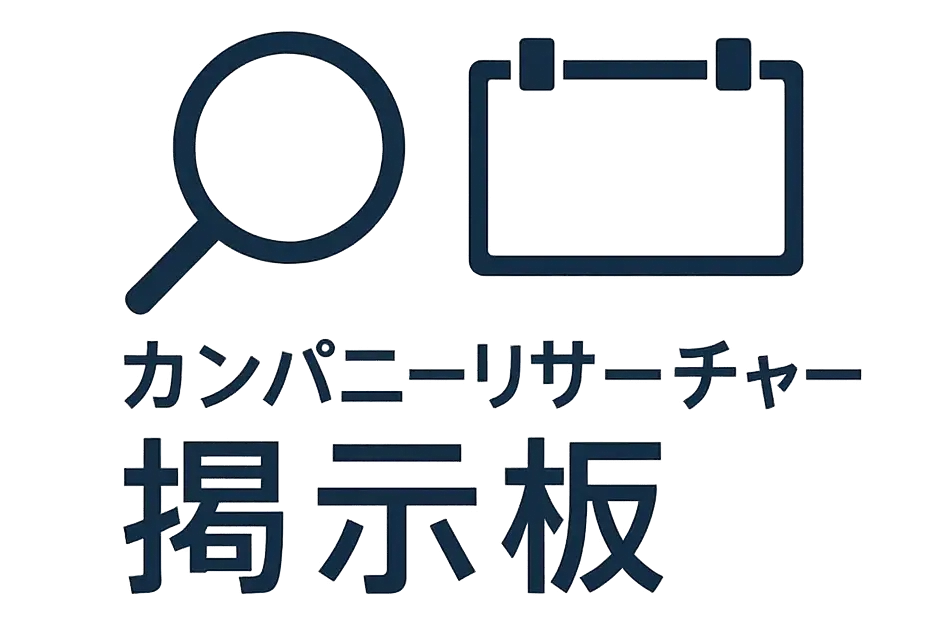
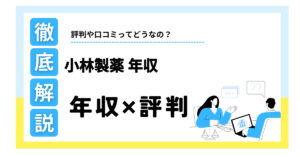
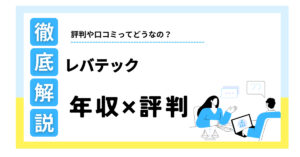
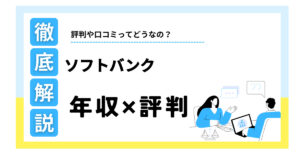
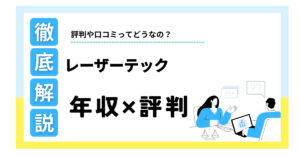
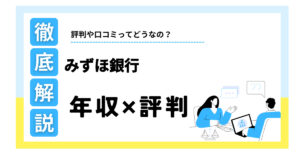
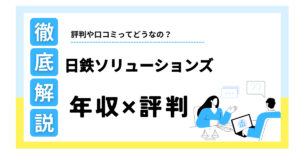
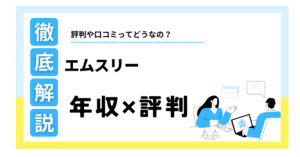
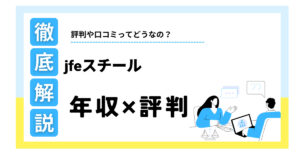
コメント