50代というキャリアの大きな節目に立ち、「このままで良いのだろうか」「転職したら年収はどうなるんだろう」と不安を感じていませんか?長年勤めた会社での役職定年が見え始めたり、会社の将来性に疑問を感じたりと、キャリアについて真剣に考える機会が増える年代です。特に気になるのが、生活に直結する「年収」の問題。50代の転職は、年収が下がりやすいという話も耳にし、一歩を踏み出すのをためらってしまう方も少なくないでしょう。
しかし、悲観する必要はありません。50代の転職は、決してネガティブなものではなく、これまでの豊富な経験やスキルを活かして、より充実したセカンドキャリアを築く絶好の機会となり得ます。重要なのは、正しい情報をもとに、しっかりとした「戦略」を立てて臨むことです。
この記事では、公的なデータを基にした50代の転職と年収のリアルな実態から、年収を維持・向上させるための具体的な戦略、さらには後悔しないためのキャリアの考え方までを網羅的に解説します。この記事を読み終える頃には、ご自身の市場価値を客観的に把握し、自信を持って次の一歩を踏み出すための道筋が見えているはずです。
【データで見る】50代の転職と年収のリアル
転職活動を始める前に、まずは客観的なデータを知り、現在地を正確に把握することが重要です。ここでは、公的機関のデータを基に、50代の年収と転職の実態を明らかにします。
50代の平均年収と中央値【男女・産業別】
国税庁が発表した「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、50代の平均年収は以下のようになっています。
- 50代前半(50~54歳): 全体 539万円(男性 682万円、女性 340万円)
- 50代後半(55~59歳): 全体 546万円(男性 702万円、女性 329万円)
男性はキャリアのピークを迎え年収が高水準にある一方、女性は非正規雇用の割合も高く、男女間で大きな差が見られます。
また、より実態に近いとされる「中央値」(データを大きさ順に並べたときに中央に来る値)は、平均値よりも低くなる傾向があります。正確な統計はありませんが、一般的に平均年収の7~8割程度が目安とされています。
さらに、産業別に見ると年収には大きな差があります。
| 産業 | 平均給与 |
|---|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 747万円 |
| 金融業,保険業 | 656万円 |
| 情報通信業 | 632万円 |
| 製造業 | 533万円 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 268万円 |
ご自身の年収や業界がどの位置にあるのかを把握することが、キャリア戦略を立てる第一歩となります。
転職による年収の変化|「増加」と「減少」の割合は?
では、50代が転職した場合、年収はどのように変化するのでしょうか。厚生労働省の「令和4年 雇用動向調査結果」を見てみましょう。
| 年齢階級 | 賃金が「増加」した割合 | 賃金が「減少」した割合 | 賃金が「変わらなかった」割合 |
|---|---|---|---|
| 45~49歳 | 36.6% | 34.6% | 28.2% |
| 50~54歳 | 31.4% | 40.2% | 28.4% |
| 55~59歳 | 28.9% | 43.1% | 27.5% |
| 60~64歳 | 22.1% | 55.0% | 22.9% |
このデータが示す通り、50代の転職では年収が「減少した」人の割合が「増加した」人を上回っています。 これは厳しい現実ですが、見方を変えれば、約3割の人は年収アップを実現していることも事実です。この「3割」に入るために何が必要なのかを考えることが、成功の鍵となります。
なぜ50代の転職は年収が下がりやすいのか?3つの構造的理由
年収が下がりやすい背景には、いくつかの構造的な理由が存在します。
- 役職の変化(ポストダウン):
前職で部長や課長などの高い役職に就いていた場合でも、転職先で同等のポストが用意されるとは限りません。特に大手企業から中小企業への転職では、役職が下がり、それに伴い役職手当などがなくなることで年収がダウンするケースが多く見られます。 - 年功序列型賃金からの脱却:
日本の多くの企業では、今もなお年齢とともに給与が上がる年功序列型の賃金体系が残っています。転職すると、この勤続年数がリセットされ、新しい会社の成果主義や職務給に基づいた評価制度に移行するため、結果的に年収が下がることがあります。 - 未経験分野への挑戦:
キャリアチェンジを目指し、これまでとは異なる業界や職種に挑戦する場合、即戦力とは見なされにくく、ポテンシャル採用に近い形になるため、年収は下がるのが一般的です。セカンドキャリアの充実感を優先する場合の選択肢となります。
これらの理由を理解しておくことで、転職活動において現実的な目標設定ができ、年収交渉の際にも冷静な判断を下せるようになります。
【年収アップ・維持】50代転職の成功パターンと求められる人材像
厳しいデータもありますが、戦略次第で年収を維持、あるいは向上させることは十分可能です。ここでは、成功している50代に共通する3つのパターンと、企業が50代に何を期待しているのかを解説します。
成功パターン①:専門性・マネジメント経験を活かす同業界・同職種転職
最も年収を維持・アップしやすい王道パターンです。これまで培ってきた専門性やマネジメント経験をダイレクトに活かせる同業界・同職種への転職は、企業側にとっても教育コストがかからない「即戦力」として非常に魅力的です。
- 例: 自動車部品メーカーの品質管理部長 → 他の部品メーカーの品質保証責任者
- ポイント: ニッチな分野での深い知見や、部下を率いてプロジェクトを成功させた具体的な実績は高く評価されます。職務経歴書では、成果を数値で示すことが極めて重要です。
成功パターン②:成長産業・人手不足の業界への挑戦
もし現在の業界が将来性に乏しいと感じるなら、思い切って成長産業や人手不足が深刻な業界へ舵を切るのも有効な戦略です。
- 成長産業の例:
- IT/DX分野: DX推進コンサルタント、SaaS企業の営業・カスタマーサクセス
- 医療/介護分野: 施設の管理職、運営責任者
- ポイント: これらの業界では、年齢よりもスキルや経験が重視される傾向があります。特に、異業界で培ったマネジメント経験を、成長産業の組織作りに活かせる人材は引く手あまたです。必要であれば、50代からのリスキリング完全ガイド|おすすめ資格と学習法を参考に、新たなスキルを学ぶ意欲を見せることも評価に繋がります。
成功パターン③:ポータブルスキルを武器に異業種へ
業界経験がなくても、業種を問わず通用する「ポータブルスキル(持ち運び可能な能力)」を武器に、異業種で活躍する道もあります。
- ポータブルスキルの例:
- 課題解決能力
- プロジェクトマネジメント能力
- 交渉力・調整力
- ロジカルシンキング
- ポイント: 「前職の〇〇という課題に対し、△△というアプローチで解決し、□□という成果を出した経験は、貴社の事業課題である××にも応用できます」というように、自身のスキルが転職先でどう貢献できるかを具体的に言語化できるかが鍵となります。
企業が50代に本当に期待する3つの役割
企業が50代を採用する際、給与に見合う働き以上の付加価値を期待しています。
- 若手の育成・指導: 豊富な経験に基づく的確なアドバイスで、若手社員の成長を促すメンターとしての役割。
- 組織の安定化: 困難な状況でも動じない冷静な判断力や人間力で、組織の精神的支柱となる役割。
- 豊富な人脈の活用: 長年のキャリアで築いた社内外のネットワークを、新たなビジネスチャンスに繋げる役割。
面接では、これらの期待を理解した上で、自身の経験がどのように貢献できるかをアピールすることが、他の候補者との差別化に繋がります。
【年収ダウン】を許容してでも得られる価値とは?後悔しない転職の考え方

転職の目的は、必ずしも年収アップだけではありません。あえて年収ダウンを受け入れ、お金以外の価値を手に入れるという選択も、50代のキャリアにおいては非常に重要です。
年収と引き換えに得られるメリット
年収が下がることと引き換えに、以下のような非金銭的な報酬を得られる可能性があります。
- ストレス軽減: 過度な責任やプレッシャー、長時間労働から解放され、心身の健康を取り戻す。
- 勤務地の自由: 地元に戻って親の介護をする、自然豊かな場所で働くなど、希望の場所で生活する。
- 可処分時間の増加: 通勤時間が短縮されたり、残業がなくなったりすることで、趣味や家族、自己投資に使える時間が増える。
これらの要素は、人生の幸福度、すなわちQOL(Quality of Life)を大きく向上させます。
未経験職種へのキャリアチェンジ(セカンドキャリア)の心構え
50代で全く新しい分野に挑戦する場合、年収ダウンは覚悟しなければなりません。その上で、後悔しないためには以下の心構えが不可欠です。
- 謙虚に学ぶ姿勢: プライドは一旦脇に置き、年下の先輩や上司から素直に教えを乞う。
- 継続的な学習意欲: 新しい知識やツールを積極的に学び続ける。
- 経験の応用力: これまでの経験を、新しい環境でどう活かせるかを常に考える。
給与は下がっても、新しい挑戦がもたらす充実感や、そこで得られるスキルは、60代、70代の人生を豊かにする大きな資産となるでしょう。
「生涯賃金」と「可処分時間」でキャリアを再評価する
目先の年収の増減に一喜一憂するのではなく、「生涯賃金」と「可処分時間」という2つの物差しでキャリアを評価してみましょう。
- 生涯賃金: 例えば、転職で年収が100万円下がっても、ストレスが減って健康を維持できれば、将来かかるはずだった医療費が数十万円浮くかもしれません。また、定年が延長されたり、長く働ける仕事に就くことで、結果的に生涯で稼ぐ総額は増える可能性もあります。
- 可処分時間: 増えた自由な時間で副業を始めれば、新たな収入源を確保できます。また、自己投資に時間を使うことで、数年後にさらに良い条件で転職できる可能性も生まれます。
短期的な視点ではなく、人生全体を豊かにするという長期的な視点を持つことが、後悔しない選択に繋がります。
50代の転職で年収を上げる・維持するための具体的な5大戦略
ここからは、50代の転職を成功に導き、年収を上げる・維持するための具体的な戦略を5つのステップで解説します。これらを体系的に実行することが、理想のキャリア実現への近道です。
戦略①:キャリアの棚卸しと実績の数値化
転職活動の出発点は、徹底した自己分析、すなわち「キャリアの棚卸し」です。これまでのキャリアを振り返り、以下の点を具体的に書き出してみましょう。
- どのような課題に対して(Situation)
- 何を考え、どのような役割を担い(Task)
- どのように行動したか(Action)
- その結果、どのような成果が出たか(Result)
特に重要なのが、成果を可能な限り数値で示すことです。
- 悪い例: 「営業として売上に貢献した」
- 良い例: 「新規開拓チームのリーダーとして、前年比120%の売上目標を達成。個人としても部署トップの5,000万円の売上を記録した」
この作業を通じて、自身の強みや専門性が明確になり、説得力のある職務経歴書の作成や面接でのアピールに繋がります。
【多くの方が見落としがちなポイント】
成功体験だけでなく、「失敗談」や「困難を乗り越えた経験」も貴重なアピール材料になります。50代に求められるのは、完璧な経歴ではなく、困難な状況にどう向き合い、そこから何を学び、次にどう活かしたかという「人間的な深み」です。失敗を乗り越えた経験は、ストレス耐性や課題解決能力の証明にもなります。
戦略②:市場価値の把握と戦略的スキルアップ(リスキリング)
自己分析で明らかになった自分のスキルセットが、現在の転職市場でどれくらいの価値を持つのか、客観的に把握することが重要です。
【シナリオ例:転職エージェントとの面談】
キャリアアドバイザー: 「A様、これまでのご経歴を拝見しました。特に、5年間の海外工場立ち上げのご経験は非常に高く評価できます。現在の転職市場ですと、同業界であれば年収800万~950万円あたりが相場感となります。」
応募者Aさん: 「なるほど。もし、年収1,000万円以上を目指すとなると、何が足りないでしょうか?」
キャリアアドバイザー: 「素晴らしい意欲ですね。もし可能であれば、昨今需要が高まっているDX関連の知見、例えば業務プロセスのデジタル化を主導したご経験などをアピールできると、外資系企業のハイクラス求人も視野に入り、年収1,000万円以上も十分に狙えます。今からでも関連資格の勉強を始めるのはいかがでしょうか?」
このように、転職エージェントとの面談や、転職サイトのスカウト機能を利用することで、自身のリアルな市場価値(想定年収)を知ることができます。もし、市場の需要と自身のスキルにギャップがあれば、DX関連スキルやプロジェクトマネジメント(PMP)など、戦略的なリスキリングを検討しましょう。
戦略③:求人動向と成長業界のリサーチ
やみくもに応募するのではなく、どの業界・企業が50代を積極的に採用しているのか、最新の求人動向をリサーチすることが成功確率を高めます。
- 企業のウェブサイト: 「採用情報」だけでなく、「IR情報(投資家向け情報)」もチェックしましょう。中期経営計画などから、企業が今後どの事業に力を入れようとしているかが分かり、求められる人材像を推測できます。
- 業界ニュース: 日経新聞や業界専門誌などで、市場が伸びている業界、M&Aが活発な業界の動向を掴みます。
- 転職サイト: 「50代 活躍中」「ミドル歓迎」などのキーワードで検索し、どのような求人が多いか傾向を分析します。
こうした地道なリサーチが、ミスマッチのない、満足度の高い転職に繋がります。
戦略④:転職エージェントの戦略的活用法
50代の転職活動において、転職エージェントは心強いパートナーです。特に、一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有している点は大きなメリットです。
【シナリオ例:エージェントからの提案】
応募者Bさん: 「C社の求人に魅力を感じており、応募したいのですが。」
キャリアアドバイザー: 「承知いたしました。C社も素晴らしい企業ですが、実は先日、非公開でD社から同ポジションの求人をいただきました。D社は現在、組織の若返りを進めている一方で、若手を指導できるベテラン層を求めており、B様のようなマネジメント経験を非常に高く評価しています。給与テーブルもC社より高く、年収交渉の余地も大きいと考えられますが、いかがでしょうか?」
成功の鍵は、複数のエージェントに登録し、自分に合ったキャリアアドバイザーを見つけることです。特徴の異なるエージェント(ハイクラス向け、ミドル特化型など)を使い分け、多角的な視点からアドバイスをもらうことで、思わぬ優良求人に出会える可能性が高まります。
戦略⑤:雇用形態の柔軟な検討(正社員・契約・業務委託・顧問)
年収や働き方の希望を叶えるために、正社員という選択肢に固執しないことも有効な戦略です。
- 契約社員: 特定のプロジェクトに期間を区切って参画。専門性を活かしやすく、プロジェクト単位で高い報酬を得られる可能性がある。
- 業務委託(フリーランス): 企業と対等な立場で契約を結び、成果物に対して報酬を得る。働く時間や場所の自由度が高い。
- 顧問: 週に1~2日といった稼働で、経営層にアドバイスを行う。豊富な経験と人脈を活かし、高い時間単価で働くことが可能。
これらの働き方は、高い専門性が求められる分、時間あたりの単価が高くなる傾向があります。結果的に、年収を維持・向上させながら、自由な時間を確保するという理想の働き方を実現できるかもしれません。
転職活動を成功に導く実践的アクションプラン

戦略を立てたら、次はいよいよ実践です。ここでは、具体的なアクションについて解説します。
50代の魅力が伝わる履歴書・職務経歴書の書き方
職務経歴書は、単なる業務の羅列であってはいけません。応募企業の課題を推測し、「自分の経験が、その課題解決にどう貢献できるか」という視点で書くことが重要です。
- 要約を冒頭に: 職務経歴の冒頭に200~300字程度の要約を記載し、採用担当者が短時間であなたの強みを理解できるように工夫する。
- 実績は具体的に: 「戦略①」で整理した内容を基に、具体的な数値を交えて実績をアピールする。
- マネジメント経験: 部下の人数、予算規模、達成した目標などを具体的に記述する。
- 情報の取捨選択: 応募ポジションに関連性の高い経験を中心に記述し、アピールポイントを絞る。2~3枚程度にまとめるのが理想です。
より詳細な書き方は、失敗しない職務経歴書の書き方【50代向け例文付き】も参考にしてください。
経験値が問われる面接の対策と年収交渉術
50代の面接では、若手とは異なる、経験の深さを問う質問がされます。
- 想定される質問への準備:
- 「なぜこの年齢で転職をお考えなのですか?」
- 「年下の上司や部下と、うまく連携できますか?」
- 「ご自身の健康管理で気をつけていることはありますか?」
- 「これまでのキャリアでの最大の失敗と、そこから学んだことは何ですか?」
これらの質問に対し、ポジティブかつ誠実に回答できるよう準備しておきましょう。
年収交渉は、内定が出て、企業側から具体的な提示があった後に行うのが基本です。自身の市場価値、企業の給与水準、そして生活に必要な最低ラインを考慮し、「〇〇という経験・スキルを活かして貴社に貢献できると考えており、年収△△万円を希望いたします」と、希望額とその根拠を冷静に伝えましょう。
活用すべき情報収集チャネル
チャンスを最大化するため、情報収集のチャネルは複数持ちましょう。
- 転職サイト・エージェント: 最も基本的なチャネル。求人検索だけでなく、スカウトサービスの登録は必須。
- リファラル採用: 前職の同僚や取引先などからの紹介。信頼性が高く、ミスマッチが少ないため、積極的に活用したいチャネル。日頃から良好な人間関係を築いておくことが重要。
- ビジネスSNS(LinkedInなど): 企業の採用担当者やキーパーソンに直接アプローチしたり、業界の最新情報を収集したりするのに有効。
【目的別】50代におすすめの転職エージェント・転職サイト

自分に合った転職サービスを選ぶことが、成功への近道です。ここでは目的別に3つのタイプをご紹介します。
ハイクラス・管理職向けエージェント
年収800万円以上を目指し、管理職や専門職としてのキャリアをさらに高めたい方におすすめです。
- JACリクルートメント: 管理職・専門職・外資系企業に強み。コンサルタントの質が高く、丁寧なサポートに定評がある。
- ビズリーチ: 登録するとヘッドハンターや企業から直接スカウトが届くプラットフォーム。自分の市場価値を知るのにも最適。
ミドル・シニア層特化型サービス
50代の転職支援実績が豊富で、年齢の壁を感じにくいサービスです。
- FROM 40: 40代・50代専門の転職サイト。ミドル・シニアを積極採用している企業の求人が集まる。
- マイナビミドルシニア: 大手マイナビが運営する40~60代向けのサービス。求人紹介から人材紹介まで幅広く対応。
幅広い求人を扱う大手総合型エージェント
まずは選択肢を広く持ちたい、キャリアの方向性が定まっていないという方におすすめです。
- リクルートエージェント: 業界最大級の求人数を誇る。非公開求人も多く、幅広い選択肢から検討可能。
- doda: 求人紹介とスカウトサービスの両方が利用可能。キャリアアドバイザーのサポートも手厚い。
これらのサービスを2~3社併用し、それぞれの強みを活かすのが賢い使い方です。
50代の転職と年収に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、50代の転職で多くの方が抱える疑問にお答えします。
Q1. 未経験の業界・職種への転職は本当に可能ですか?
A1. 可能です。ただし、相応の覚悟と準備が必要です。
未経験分野への転職では、年収が一時的に下がることを受け入れる必要があります。その上で、成功の鍵となるのは「謙虚さ」と「これまでの経験の応用力」です。プライドを捨てて年下から学ぶ姿勢と、前職で培ったプロジェクトマネジメント能力や課題解決能力が、新しい環境でどのように活かせるかを具体的に説明できれば、道は開けます。充実感を優先するセカンドキャリアの選択肢として、非常に価値のある挑戦です。
Q2. 50代の転職で、本当に役立つ資格は何ですか?
A2. 資格単体で評価されることは少なく、「実務経験との掛け合わせ」が重要です。
その上で、キャリアの価値を高める可能性のある資格として以下が挙げられます。
- DX・IT関連: ITストラテジスト、AWS認定資格など。あらゆる業界で需要があります。
- マネジメント関連: プロジェクトマネージャ試験(PMP)、中小企業診断士など。経営層に近い視点での貢献が期待されます。
- 不動産・金融関連: 宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)など。専門性が高く、長く活かせる資格です。
自身のキャリアプランと市場の需要を照らし合わせて、戦略的に取得を検討しましょう。
Q3. 早期退職制度を利用すべきか迷っています。判断のポイントは?
A3. 焦って決めないことが最も重要です。
早期退職制度は、退職金が上乗せされるなど金銭的なメリットが大きい反面、「次のキャリアが決まらないうちに退職してしまい、焦りから望まない転職をしてしまった」という失敗談も少なくありません。
もし制度を利用せずに転職活動をする場合は、より慎重な計画が求められます。在職中に転職活動を行い、内定を得てから退職するのが最も安全な進め方です。退職金の上乗せがない分、転職先の条件交渉や、転職までの生活費の計画をよりシビアに行う必要があります。いずれにせよ、まずは転職エージェントなどの専門家に相談し、自身の市場価値やキャリアの選択肢を客観的に把握した上で、冷静に判断することをおすすめします。
Q4. 転職活動には、どのくらいの期間がかかりますか?
A4. 一般的に3ヶ月~半年が目安ですが、1年以上かかるケースも珍しくありません。
50代の転職は、マッチする求人が若手より少ないため、長期戦になる可能性も視野に入れておく必要があります。そのため、できる限り在職中に転職活動を開始することを強く推奨します。経済的な不安なく、じっくりと腰を据えて企業選びができるため、結果的に満足のいく転職に繋がりやすくなります。
まとめ:50代の転職は「戦略」がすべて

50代の転職は、若手のようにポテンシャルだけでは評価されません。しかし、これまでのキャリアで培ってきた豊富な経験、スキル、人脈という、若手にはない強力な武器を持っています。その価値を最大限に引き出し、成功を掴むために不可欠なのが、本記事で繰り返しお伝えしてきた「戦略」です。
最後に、重要なポイントを振り返ります。
- 現実を直視する: まずは公的データで50代の年収や転職のリアルを把握する。
- キャリアプランを明確に: 年収アップ・維持・ダウンの各シナリオを想定し、自分が何を優先したいのか価値観を定める。
- 5大戦略を実行する: 「キャリアの棚卸し」「市場価値の把握」「業界リサーチ」「エージェント活用」「柔軟な雇用形態の検討」を体系的に進める。
- 専門家を頼る: 一人で抱え込まず、転職エージェントなどのプロの力を借りる。
50代からのキャリアは、決して「消化試合」ではありません。これからの20年、30年をより豊かに生きるための、新たなスタートラインです。役職定年後のキャリアプランニング|セカンドキャリアの築き方を考え始める今こそ、行動を起こす絶好のタイミングです。悲観することなく、自信を持って、新たな一歩を踏み出してください。
免責事項
本記事は、キャリアに関する一般的な情報提供を目的としており、個別の転職活動における成功を保証するものではありません。転職サービスの選定や転職活動の実行にあたっては、ご自身の判断と責任において行ってください。また、掲載されている情報は記事執筆時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。
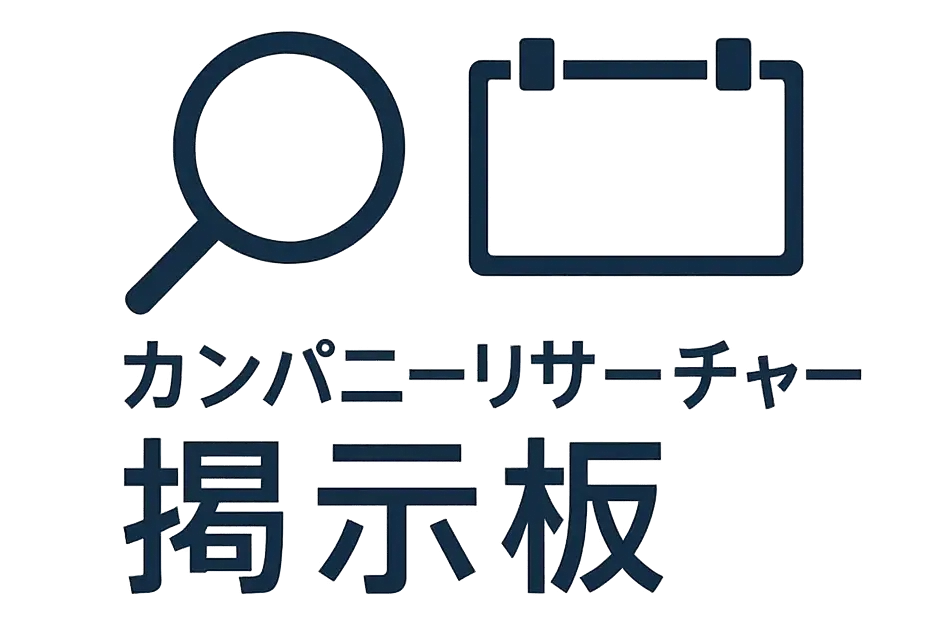
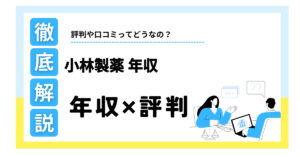
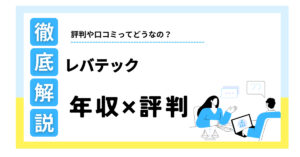
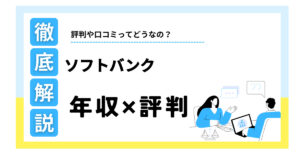
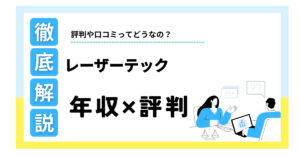
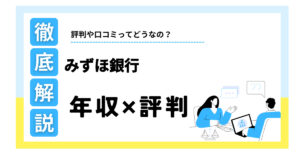
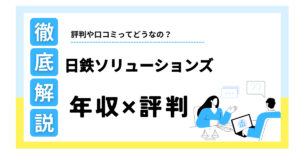
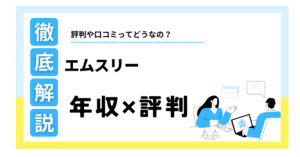
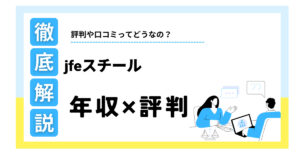
コメント